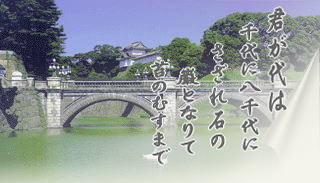
| 君が代の楽譜 |
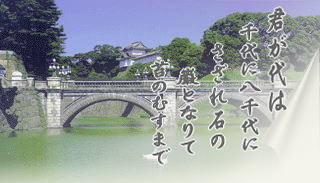 |
|||
|
| 驚き・・” 君が代に2番が・・・・ 其れに別の節が・・・・・ これは長野の「旧開智学校」を見学した時、偶然、2階の展示室の隅にあったケースの中で見つけた。 展示室の係りの方にお願いしてコピーを執って戴いた貴重なものです。 皆さんに紹介したい。 次に示す「君が代」は「古今和歌集」の中にある「わがきみは」の歌(読み人知らず)をあらためたもので、後に政府が「君が代」を祝日大祭日唱歌の一つとして1893年(明治26年)に官報に交付したものの元になったものと推測される。この唱歌の本は何時ごろのものか不明だが、文部省小学唱歌集に載っていたもので、当時、国民唱歌として多くに唄われていた事は確かの様だ。 旋律の方はと言えばまるで雅楽の調べ、何ともいえない優雅さと神秘さを感ずる。 さて、「君が代」には色々な旋律があった様で、この他に、薩摩軍楽隊教師のイギリス人ヘントン作曲のもの、林 広守の作曲等があったようだ。 現在の「君が代」は1880年(明治13年)宮内省式部寮雅楽課員、奥 好義(よしいさ)が作品募集に応じて作曲した曲(入選作品)を楽長の林 広守が補正して発表した、とある。 林 広守の作曲とはこんな経緯からと思われる。 後に、雅楽調の原曲で有った物を海軍軍楽隊教師のドイツ人エッケルトに依って洋楽風に編曲されて現在に至っていると思われる。 皆さんに紹介するこの「君が代」は文部省小学唱歌集に載っていたと言う事と、他の資料等から推察するところ「稲垣千頴(ちさと)」という人の作曲ではないかと思われる。 皆さん、わが国歌「君が代」を今一度口ずさんでみましょう。 また、下に紹介する「君が代」も歌ってみてください。日本人に生きる血に、改めて新しい何かを感じて戴けると思います。 |
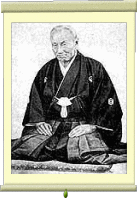
| 1 君が代は 千代に八千代に さざれ石の 巌となりて 苔のむすまで 動き行く 常磐(ときわ)かきはに かぎりもあらじ |
| 2 君が代は 千尋(ちひろ)のそこの さざれ石の 鵜のいる磯と あらはるるまで かぎりなき みよの栄を ほぎたてまつる |